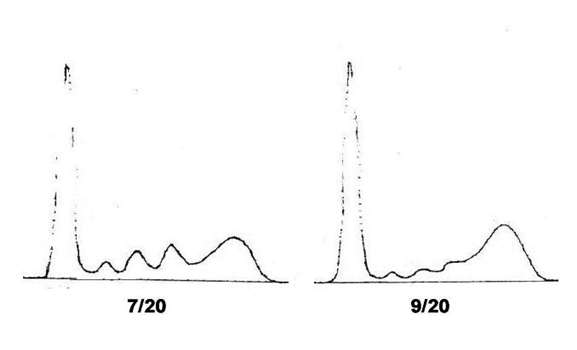
|
|
症例
69歳 女性
肝細胞癌
|
Date (g/dL) |
TP |
Alb |
α1gl |
α2-gl |
β-gl |
γ-gl |
|
7/20 |
7.2 |
3.5 |
0.28 |
0.60 |
0.78 |
2.0 |
|
9/20 |
8.0 |
4.0 |
0.18 |
0.30 |
β+γ=> |
3.5 |
|
HBs抗原陽性の肝硬変をベースに発症した単発性の肝細胞癌 (HCC) である。治療開始前、7/20時点で AST 105IU,、ALT 55IU、Ch.E 0.33 ΔpH。8/10、8/30の 2回 sponzel とマイトマイシンC 5 mg で塞栓術を施行した。 |
|
コメント |
|
文献 |
|
|
井上隆智
|
|
|