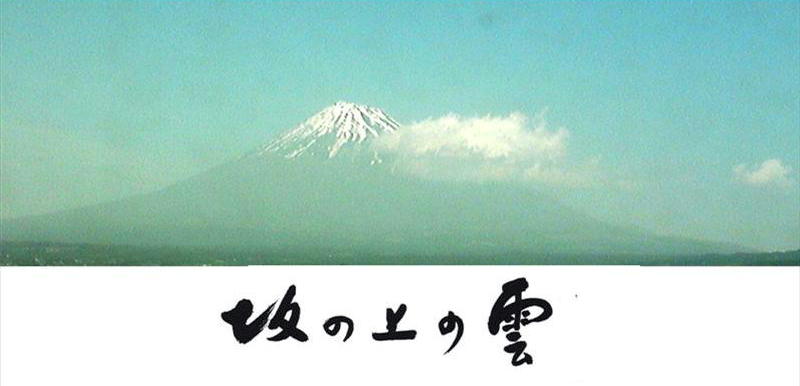
Maki と Sara の Stand Alone
NHKスペシャルドラマとして放映されている司馬遼太郎原作の「坂の上の雲」第二部で森 麻季によって歌われるテーマ曲、「Stand Alone」 に思わず心惹かれたのは私だけではないと思います。ドラマのエンドロールとともに日本アルプスの尾根筋を背景に流れるこの歌声を聴いていると吸い込まれるような不思議な感覚に捉われます。ですからドラマが終わってもこの歌が終わるまではテレビのスイッチを切ることが出来ません。この魅力は一体どこから来るのでしょうか。(この曲はCD「坂の上の雲」オリジナル・サウンドトラック2(「サントラ2」)の第24曲として収められています。註1)
Stand
Alone 作詞:小山薫堂
ちいさな光が 歩んだ道を照らす
希望のつぼみが 遠くを見つめていた
迷い悩むほど 人は強さを掴むから 夢を見る
凛として旅立つ 一朶の雲を目指し
あなたと歩んだ あの日の道を探す
ひとりの祈りが 心をつないでゆく
空に手をひろげ ふりそそぐ光あつめて
友に届けと放てば 夢叶う
はてなき想いを 明日の風に乗せて
私は信じる 新たな時がめぐる
凛として旅立つ 一朶の雲を目指し
この歌詞、そもそも「Stand Alone」とはどういう意味なのでしょうか。「自立」でよいのですかね。この歌詞は一番、二番(註2)とも最後の一行を除けば美しい日本語の文節は並んでいますが、各行、各フレーズの間には何の脈絡もありません。全体として意味不明というほかありません。あえて察するに作詞者はこの詩の最後の一行にドラマの心のすべてを託し、ほかのところは単なる前置きとしてそれらしい言葉を選んだだけのような気がします。しかも肝腎の最後の一行の、「凜」も「一朶」も耳から聞いただけではどんな文字なのかの見当すらつきません。また、使われている単語本来の標準語アクセントと歌のイントネーションがちぐはぐなところがあり、曲に歌詞をあとからつけた(?)せいではないかと思ってしまいます。それやこれやで、この詩は”歌の詞(ことば)”としてはかなり不適切なものであることは否めません。なおこの歌詞の意味については最後にもう一度触れます。
其れかあらぬか、ドラマ「坂の上の雲」の第一部では、「Time To Say Goodbye」で有名なサラ・ブライトマン(Sarah Brightman 以下サラと呼ぶ)がN響をバックにこのメロディーを歌詞のないヴォカリーズ(註3)で歌いました。ヴォカリーズの持つ独特の魅力を彼女の美しい歌声が存分に引き出しています。このような難解な歌詞を耳で追うよりは優美なヴォカリーズとして聴くほうがよほどリラックスして音楽にひたれるのだということを実感させてくれます。
久石 譲によるこの曲は意図的に、だと思いますが、N響(伴奏)バージョンでは各フレーズの最後の一語(字)はフェルマータ( :延長記号)で長めに引っ張ったあと、「スーッ」と消えるように歌い終わらせています。これは、歌詞のある森
麻季もヴォカリーズのサラも同じです。リズムとメロディーの美しさもさることながら、これもこの曲の大きな魅力になっています。そしてその一番の聴かせどころが歌い終わりのフレーズにあるのです。
:延長記号)で長めに引っ張ったあと、「スーッ」と消えるように歌い終わらせています。これは、歌詞のある森
麻季もヴォカリーズのサラも同じです。リズムとメロディーの美しさもさることながら、これもこの曲の大きな魅力になっています。そしてその一番の聴かせどころが歌い終わりのフレーズにあるのです。
ドラマの第一部と第二部とでサラと森麻季が同じテーマ曲を競演することになったわけですが、二人の歌には単に歌詞のありなしというだけではない大きな違いがあることに気がつきました。その違いの一つはまさにサラがヴォカリーズを歌い終わる一瞬に現れます。
サラが承知でやらせたのか、技術者が勝手にやったのかはわかりませんが、歌詞でいえば「・・・目指しー」に相当するサラの「・・・アー」の声が消えていくところに人工的にエコーをかけてから録音アンプのボリュームを操作してフェードアウトさせています。その証拠に歌声のバイブレーションはなくなり、「ホワーン」と終わります。水準のステレオ装置で聴けば簡単に気がつきますしテレビのスピーカーでも何とかわかると思います。サラ自身の歌声が自然に消えていくのではなく、そのような擬似的効果を電子音響技術で作っているのです。これは暗にサラがこの曲の歌い終わりのところで作曲者の意図したようには歌えなかったことを意味しているのかも知れません。
これに対し森 麻季が歌詞付きで歌っている第二部のエンディングでは、「凛として旅立つ 一朶の雲を目指し」、この短いフレーズがフォルテで劇的に始まり、デムヌエンド(dimuniendo)してピアニッシモから消え入るように終わっています。もちろん全部彼女の声のままです。バイブレーションも最後まで綺麗に聞こえます。人工操作が加えらた形跡はありません。
このように歌い終わりに聴かれる微妙な差もさることながら、サラと森 麻季の歌にはどこかもっと本質的な違いがあるような気がしてなりません。それを知る手がかりになりそうなのが「サントラ2」のCDの第13曲として収められているサラがピアノ伴奏で同じ「Stand Alone」のヴォカリーズを歌っるいるバージョンです。
これは上に述べたN響をバックにした第一部のエンディング・テーマのヴォカリーズとは違い、サラはマイクに口を近づけ(オン・マイク)て歌っています。マイクの増幅力を借りて歌うときとオペラ的に歌うときとの違いがよくわかります。容易に気がつくのは全曲を通して声の大きさの振れが小さいことです。それに、ピアノ伴奏バージョンでは各フレーズの終わりの息継ぎが明瞭に録音され、当然その都度歌声が一瞬途切れます。歌声は消え入るようには終わりません。結果、歌はややフラットなポップス調になっていて、これはこれで十分楽しめますが、作曲者が一番こだわった(と思われる)歌い終わりの余韻などはいまひとつということになります。
サラのこのピアノ伴奏バージョンを聴いたあとで改めて第一部のサラのヴォカリーズ、N響バージョン「Stand Alone」を聴いてみますと、サラは森 麻季に較べて明らかに抑揚の少ない歌い方をしているのがわかります。歌い終わりのメーキング云々よりこのほうがサラと森麻季との一番大きな違いかも知れません。そもそもヴォカリーズという歌い方自体オペラのアリアのようなダイナミックな効果を求めるものではなくて、むしろ静かな雰囲気を醸し出すための歌い方だからなのでしょう。サラがもっとも得意とするのはひょっとしてこのポップス調の歌い方なのではないかと素人考えではそのように思ってしまいます。
ちなみにオペラ歌手がポップスを歌うとどうなるか。余談ですが、かつて「夜明けの歌」などで知られる岸 洋子がオペラ歌手になるべく修練して芸大を出たにもかかわらず、膠原病(エリテマトーデス)を発病したため、体力を使うオペラ歌手になることを諦めてマイクに頼るポップス歌手に転向しました。それでもこの世界で多くの素晴らしい歌を歌いました。サラはオペラも歌えますからもちろん岸 洋子とは条件が違いますが、どこか二人の歌のイメージには重なるものがあります。
さて、第一部のサラもそうなのですが、N響をバックにした森 麻季はマイクなしでもホール全体に声が届くオペラの”アリア”のようにこの曲を歌っています。収録用のマイクはたぶん彼女からかなり離して(オフ・マイクで)置かれていたはずです。息継ぎは録音されてません(註4)。 それでもマイクは彼女の歌声を完璧に捉えています。そのドラマチックな歌の最後はピアニッシモから消え入るように終わります。N響のような大オーケストラの音量にも負けずたったひとりの歌声が透って来る、これこそまさしくオペラの歌い手の真骨頂なのでしょう。そして彼女の日本語の何と美しいこと。彼女が歌ったのでこの意味不明の歌詞にもいのちが吹き込まれたとさえ思えるほどです。
「坂の上の雲」の音楽、ことに森 麻季の「Stand Alone」は平成屈指の名演奏だと思います。その魅力は「サントラ2」のCDで十分に味わえますが、そのためにはぜひそれなりのオーディオ・システムで聴いて下さい。CD「サントラ2」の録音はダイナミックレンジ、周波数レンジともに広く、オーディオ・チェックのソースとして十分通用します。それに一枚のCDでヴォーカルを含め何種類もの楽器の音色がソロ演奏で楽しめます。第5曲、アイリッシュハープ(だと思います)を真ん中にしてチェロが右の床の上に、ヴァイオリンが左やや上にきっちり定位しますか。そしてチェロは豊かなホールトーンとリアルな胴鳴りを聴かせますか。また、後半のヴァイオリンからもはっきりと胴鳴りが聴き取れるはずですがどうですか。第13曲でサラを伴奏するフルコンサート・グランドがどっしりと目の前に見えますか。サラの息づかいが聞こえますか。そして、第19曲の大太鼓の重低音が音というより部屋の空気の揺れとして感じられますか。(低音再生能力が公称60Hzまでしかない私のサブスピーカーヤマハ10Mはこの重低音をまったく再生できません。)そして・・・
第24曲、「坂の上の雲」のエンディングで歌われる森 麻季の 「Stand Alone」 を聴くと吸い込まれるような不思議な感覚に捉われる、と冒頭で申しました。そのわけをうまく説明出来る言葉を私はまだ持っていません。彼女のコロラトゥーラ(註5)のたとえようもない清涼感に心が洗われるから、とでも言っておきましょうか。しかもその歌は最後に劇的な盛り上りをみせてからまことに静かに消えて行きます。歌が終わった瞬間の静寂は何物にも代え難く深いものです。この歌を聴いたあとには、もうほかの音楽を聴こうなどとという気分にはなれません。この曲がドラマの冒頭ではなく、エンドロールとともに歌われるのもあながち故なしとはしません。
最後に、今度の東日本大震災に際して、森 麻季はこの曲を持って東北に行き被災者を勇気づけていると聞きました。この小文のまとめを書くに当たっても「Stand Alone」の歌詞が「耳から聞いたらさっぱりわからない詩である」という意見を変えるつもりはありません。しかし、2011年の春、この歌詞をじっくり”読んで”みますと、そのひとことひとことが今日の日本人にとってまことに時宜を得た応援の詩(うた)であることに気が付きます。日清日露の国難を念頭に書かれたであろうこの詩が東北の大災害という今日のわが国難に際しても普遍的な価値を持つことを見抜いていたかのような作詞者の炯眼には心から敬意を表したいと思います。(文中敬称略)2011/4.23アップ.5/24重訂。T.Inoue
♪===========================================================================================-♪
タイトルの説明:写真は2011/5/14東海道新幹線のぞみ10号車窓より撮影。カメラはシャープ・ドコモ02A。題字はCD「サントラ2」より(揮毫は司馬遼太郎)。
註1: 放映されたドラマのエンドロールでは2番、つまり「あなたと・・・ ・・・明日の風に乗せて」乃部分は歌われていません。
註2:サラ・ブライトマンと森 麻季の「Stand Alone」はどちらもYou-Tubeで各曲通しで聴くことが出来ます。音はパソコン次第。
註3:ヴォカリーズ vocalise =(多くは一種類の)母音だけでメロディーをなぞる歌い方。「アアーアー」などと歌う。
註4 : 森 麻季が2011/5/17夜8時のNHKの歌謡番組に引っ張り出されて、ポップス演奏用の管弦楽の伴奏でこの曲を歌いましので、私はテレビ音響を私のステレオで再生して聴きました。マイクまでの距離はテレビ画面から察するに約70センチ。息づかいが聞こえる距離です。事実聞こえました。もちろん彼女は見事に歌いきりましたが、でもやはり、下手な伴奏、響の貧しいNHKホール、短いマイクまでの距離など、こんな悪条件ばかり揃った場では森 麻季といえども実力が発揮できないことがよくわかりました。「サントラ2」の森 麻季ではありませんでした。西郷輝彦の草臥れた「星のフラメンコ」のあとで森 麻季に「Stand Alone」を歌わせるなどという無体なことをさせるべきではありません。NHKは音楽を何だと思っているのでしょうか。
註5 : コロラトゥーラ(またはコロラチューラ)=coloratura 語源的にみれば color 「彩り」です。ソプラノで高音に巧みに色づけして歌うこと、また、そういう歌い方の出来る歌手のことのようです。
(謝辞:本ページ作成に当たってはオペラ歌手帯刀享子さんに助言を頂きました。)